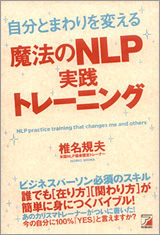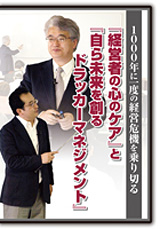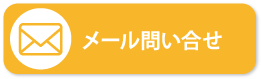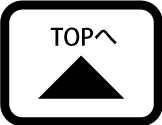【解説】ビジネス心理学|営業やマーケティングに活かせる20のコツ
投稿日:2024年2月10日 / 最終更新日:2025年1月24日

同じ商品であっても、アピール方法や説明の仕方で印象や購買意欲は大きく変わります。
ビジネスシーンで今まで以上の成果を上げたいのであれば、人の心理についてより詳しく知る必要があるでしょう。
ここでは、営業やマーケティングに活かせるビジネス心理学の効果について詳しくご紹介します。
目次 [閉じる]
ビジネス心理学の目的
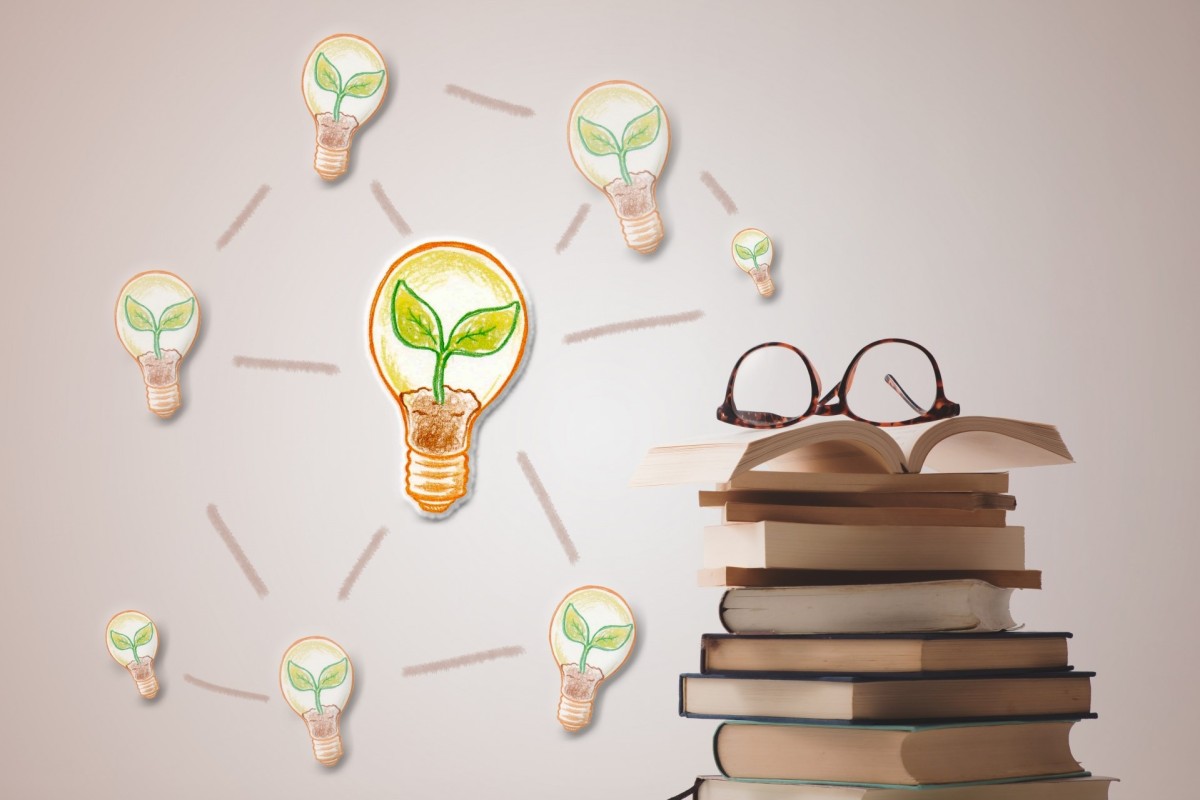
ビジネス心理学の目的は、お客様に満足していただけるサービスを追求しつつ、サービスを提供する働く人の満足も高めていくことです。
働く人の幸せとモチベーションを高める
営業にはノルマがあり、数値化される成果があります。
他人よりも良い成果を上げて評価されたいという気持ちや、営業で成果を上げられないと自分はダメだなと感じてしまいがちです。
他人の成功を妬んだり、陰口を叩くようになってしまうケースもあります。
ビジネス心理学を学ぶことでそのような自分の内面に気づき、良い方向に気持ちを向けることができます。
結果、働く人の幸せとモチベーションを高めることになるのです。
お客様に最高のサービスを提供する
お客様自身も、自分の内面の本当の気持ちに気づけていないものです。
隠れているニーズにアプローチすることができれば、そのニーズを満たす商品やサービスを提供することで、お客様の満足度は高まります。
ビジネス心理学は、マーケティングや営業を通して最高のサービスを提供するためにも必要なのです。
ビジネス心理学で絶対に避けること

ビジネス心理学の目的を達成することで、評判が高まったり、売上が伸びたりしていきます。
ただし、目的を見失って成果だけを求めることにならないよう注意しましょう。
まわりを思い通りに動かそうとするビジネス心理学の危険性
成果だけに注目してビジネス心理学を利用すると、価値の低い商品をあたかも価値の高い商品に見せて、高額な請求をするような悪徳商法になってしまう危険性があります。
詐欺はその典型でしょう。
ですから、ビジネス心理学の目的は絶対に見失わず、お客様と働く人がWin-Winの関係を築けるように意識しましょう。
相手を操作しようとする操作主義は厳禁
話し方や見せ方といった、相手への働きかけによって商品やサービスの印象を変えたり、購買意欲を向上させたりすることがビジネス心理学を利用していくと可能なのですが、悪用は厳禁です。
ビジネス心理学と聞くと、相手の心理を操作して成果を上げることだと勘違いしている人も多いかもしれません。
お客様の要望やニーズより、商品やサービスを売ることを重視してしまい、不安を煽ったり過度な期待を持たせたりなど、操作主義的な使い方では、お客様との信頼関係を壊すことになりかねないので注意しましょう。
それではここからは、営業やマーケティングに活かせる心理について20項目に分けて解説していきます。
無意識に人間関係で用いられている心理6選

ここでは、無意識に人間関係で用いられている心理や認知バイアスについて6項目紹介していきます。
認知バイアスとは、自分の思い込みや周囲の環境といった先入観により、非合理的な判断をしてしまう認知の歪みや偏りのこと。
自分自身の心理が無意識にどんな働きをしているのかを知ることで、顧客との良好な人間関係の構築をさまたげている原因や自らの成長を阻害している要因がわかり、改善につなげることができます。
セルフハンディキャッピング
人は無意識のうちに自分の自尊心を守るための言動をとっています。
その1つが「セルフハンディキャッピング」です。
失敗しても評価を下げず、成功するとより評価してもらうための予防策で、例えば「実は風邪をひいて体調を崩していたから、次のプロジェクトの準備が上手くできなかったんだ」といったような発言です。
これでプロジェクトが上手くいけば体調を崩してでも頑張ったと評価されますし、失敗しても体調が悪かったので仕方がないと評価を下げずに済みます。
自己奉仕バイアス(セルフ・サービング・バイアス)
セルフハンディキャッピングと似たような心理の仕組みに「自己奉仕バイアス」があります。
失敗したら外的要因のせいで、成功したら自分のおかげという自尊心を守る心理です。
自己奉仕バイアスが働くと、例えば「営業で商品が売れなかったら、それは商品が他社のものよりも性能が低いからで、売れたら自分の営業が上手くいったから」と考えます。
そうすることで営業に失敗しても自尊心を傷つけずに済むのです。
自己評価維持モデル
現代はSNSの普及によって、他人の暮らしや仕事ぶりなどが表面化されて、自分と比較しやすくなっています。
自分自身の現状に不満を持っている場合、成功者を妬んだり、誹謗中傷で妨害したりする悪影響があるのですが、それは相手との距離や自分自身がどこまで関与しているのか、相手が自分よりどれだけ優れているのかといった「自己評価維持モデル」によって変化します。
SNSで中傷することで相手の価値を下げたり、それに同調してくれる仲間を見つけたりすることで、自分を安定させようとする心理が働いているのです。
社会的比較理論
優れた上司に出会って、「自分は今このレベルだが、この人のようになりたい」と上方比較するケースと、自分よりも不幸な境遇の人を見て安心する下方比較のケースのような認知バイアスを「社会的比較理論」と呼びます。
上方比較できるとモチベーションがアップして成長できますが、下方比較の場合は現状に甘んじて成長しにくくなります。
透明性の錯覚(透明性錯誤)
実際は相手が自分のことをよくわかっていないのに、自分の考えていることや感情が相手に見透かされていると思い込んでしまう傾向を「透明性の錯覚」と呼びます。
例えば、ウソをついたときに相手にバレていると必要以上に思い込んでしまう心理です。
スポットライト効果
透明性の錯覚と似たような心理の仕組みに「スポットライト効果」があります。
自分のことをみんなが見ていて、注目されていると思い込んでしまう心理です。
実際はほとんどの人が気にしていなかったり、見ていないものなのですが、この傾向が強いと常に他人の目を気にしたり、スピーチの際に必要以上に緊張してしまいます。
モチベーションアップに使える心理学4選

次に解説する4つは、自分だけでなく同僚、チームのメンバーなど、相手のモチベーションアップに効果のあるビジネス心理学です。
自分や周りの自主的な行動が促進されることで、チーム全体の生産性向上に役立ちます。
内発的動機づけ
「内発的動機づけ」は、興味関心といった内面に湧き上がる気持ちが行動の動機になる状態です。
例えば「今の仕事にやりがいを感じている」のであれば、自分で創意工夫をしながら意欲的に取り組むことができます。
外発的動機づけ
逆に報酬や評価または罰則など外的要因が行動の動機になる状態が、「外発的動機づけ」です。
例えば「ノルマをクリアするとボーナス増額」や「ノルマを達成できなければ人事評価が下がる」といった条件を提示することで、興味や関心が薄い人のモチベーションをアップさせるのに効果的です。
アンダーマイニング効果
理想は内発的動機づけによって自ら率先して行動していくことなのですが、それに対して、「ノルマを達成すると報酬を与える」という外発的動機づけをすることにより、当初の目的が変わり、自己決定感や有能感の低下により意欲が削がれてしまう心理を「アンダーマイニング効果」と呼びます。
エンハンシング効果
アンダーマイニング効果がモチベーションのダウン効果があるのに対し、言語による報酬によって内発的動機づけをサポートし、モチベーションをアップさせる手法があります。
それが「エンハンシング効果」です。
例えば、結果や成果ではなく、そこまでの努力の過程に注目してみんなの前で称賛するといった働きかけをすることで、さらに内発的動機づけは高まります。
営業に使える心理テクニック4選
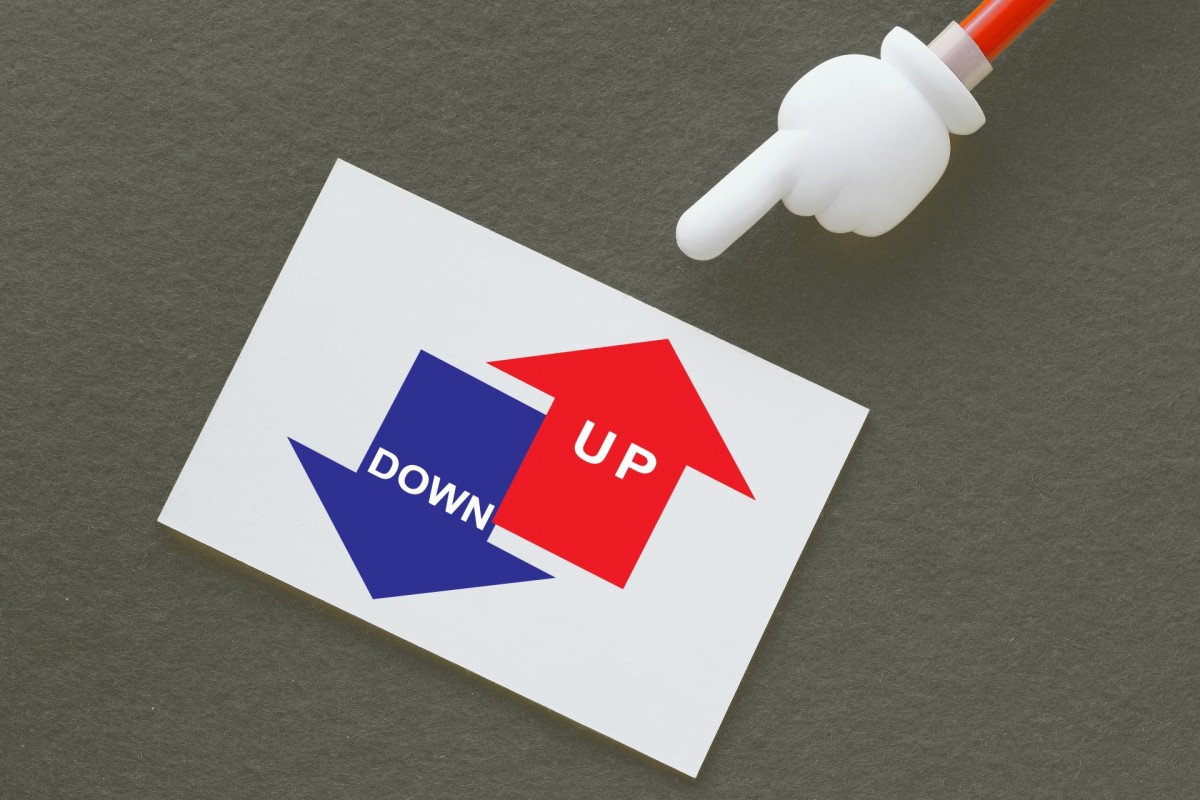
次に解説する4つについては、営業で効果を発揮するビジネス心理学のテクニックで、お客様の購買意欲を高めることに役立ちます。
逆に購買意欲を低下させる効果についても触れていますので注意してください。
スリーパー効果
情報がどのくらい記憶に刷り込まれるのかという点では、「スリーパー効果」と呼ばれるものがあります。
信憑性の低い情報でもインパクトがあると、時間の経過と共に記憶に残るという心理です。
例えば、営業でインパクトを持たせた説明を繰り返ししていくことによって、最初は反応が鈍くても、やがて興味を持ってもらうことができる可能性があります。
テンション・リダクション効果
張り詰めた緊張感が続いた後は緊張感が緩むという心理を用いた「テンション・リダクション効果」があります。
手に入れたい高価な商品を購入するか熟考していて、いざ購入すると、その価格よりも安いオプション製品などについてはもう悩まずに購入してしまう心理現象です。
ブーメラン効果
外的要因によって、始めとは真逆の心理になってしまう認知バイアスを「ブーメラン効果」と呼びます。
例えば、これからこの商品を購入しようという気持ちになったタイミングで、店員から商品説明されて購入することを勧められると、途端に意欲を失ってしまうケースがあります。
自分の行動の自由が制限されたと無意識のうちに受け止めるからです。
フレーミング効果
焦点の当て方でまったく別の印象を与える認知バイアスを「フレーミング効果」と呼びます。
例えば、健康食品で「90%の対象者に効果があった」とアピールするのと「10%の対象者には効果がなかった」とアピールするのでは、より健康になった点を強くアピールしている前者の方が購買意欲を高めることができます。
マーケティングで使える行動心理学6選

最後に、マーケティングで効果を発揮するビジネス心理学を6つ解説していきます。
この手法を用いることで、顧客の求めるニーズを効果的に製品やサービスの魅力に反映させたり、よりいっそう市場に受け入れられやすい形で伝えたりすることができます。
リフレーミング効果
短所であったと思われていた部分も、見方によっては長所になります。
そのためには、相手の注目するフレームを変えてもらう必要があります。
これが「リフレーミング効果」と呼ばれるもので、例えば、この製品は高いという価格への注目を、
この製品を長く使うことでどのようなメリットを得られるのか想像してもらうことで製品への印象が変わってきます。
クレショフ効果
別々のものを連続で見せることによって、無意識に関連づける心理を「クレショフ効果」と呼びます。
CMで高級車にオシャレで気品のあるカップルが乗っているのを見ると、この高級車に乗るとこんな雰囲気の人に自分もなれるというイメージが沸きます。
お客様がCMを見て、自分でも気づかなかった価値観に気づいて購入意欲が高まる可能性があるのです。
アンカリング効果
最初に示された数値が無意識のうちに基準になっているため、その後にそれよりも安い価格を示されるととてもお得に感じる心理を「アンカリング効果」と呼びます。
メーカー小売価格を示して、そこから30%割引きの価格を提示すると、最初からその価格を提示するよりも購買意欲は高まります。
ザイオンス効果
お客様と接触回数を増やすことで、好感度や理解度は高まります。
これを「ザイオンス効果」と呼びます。
毎日しつこく訪問しては逆効果ですが、適度な間隔でその都度少し説明の仕方を変えることで訪問者への好感度が高まり、製品への興味も増します。
例えばTVやYouTubeのCMで繰り返し告知していくと、ザイオンス効果が発揮されます。
カクテルパーティー効果
自分の名前や自分に興味関心ある話題であれば、騒がしい会場にいたとしても反応する心理を「カクテルパーティー効果」と呼びます。
そのため、ターゲットを絞って製品に興味を持ってもらう場合は「小さなお子様のいる家庭限定」や「これから結婚を考えている方限定」といった呼びかけを入れる手法が効果的です。
ウィンザー効果
当事者の発言よりも、第三者の意見の方が信頼されやすい心理を「ウィンザー効果」と呼びます。
自社のWebサイトで製品のメリットを紹介する以上に、SNS上で製品を購入し、実際に使ってみたユーザーの感想などの口コミやレビューは、製品の価値をアピールする絶好の機会です。
まとめ

紹介してきたように人の心理は、こちらの働きかけの仕方によって大きく変わります。
製品やサービスの価値を、正しく、多くの人に伝え、お客様に満足感や幸福感を味わってもらうためにもビジネス心理学はとても重要です。
ぜひビジネス心理学の目的を忘れずに、お客様も働く人も幸せになれる働き方を追求していきましょう。