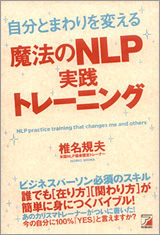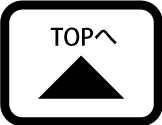理知としての言葉。
投稿日:2025年4月21日 / 最終更新日:2025年4月24日
「言葉という普遍を、理知で使うのはもったいない。」
ある言葉のプロから、そんな一言を聞いたとき、心がざわついた。
理知で言葉を使う?それがもったいないって?
ほうっておけないじゃないですか。
そもそも、理知とは何か。
筋道を立てて理解し、判断する知的能力。理性と知性のバランス。
……なるほど。確かに正しそうに響く。
でも、こんなことを考える。
たとえば、誰かと気まずくなってしまったとき。
私たちはきっと、「あーぁ、どうしてかなぁ……」と悩むだろう。
そんなある日、相手からこんな言葉が届いたとしたらどうだろう。
「ありがとう。この間の件だけれど、いろいろ考えた。
すれ違うって、いいね。
いろいろなことに気づけた。
生きているから、そうなるね。
ありがとう。」
これって、理知的な“自覚”じゃない。
もっとずっと、身体の奥から“覚っちゃった”感じ。
そこに並ぶのは、普遍的な言葉たちだ。
「ありがとう」
「考えた」
「気づけた」
「生きている」
どれも、時代や立場を超えて、人の内側とつながっている言葉。
そんな言葉に触れると、やさしさを感じる。
自分の深い部分と、そして相手の深い部分と、静かにつながれる気がする。
けれど、現実はどうだろう。
「あのとき、何かが悪かった」
「あのとき、こうして欲しかった」
「あのときのことって、どういうことだったの?」
そんなふうに、“あのとき”を理知で解き明かそうとする会話が多い。
出来事を筋道立てて理解しようとする。それが普通のやり方なのかもしれない。
けれど、ひとりひとり、生き方も感受性も違うのに。
そんな相対的なものの見方だけでやりとりしていたら、社会で生きるのは、きっとどこか窮屈になる。
あるいは、もっと距離を取って、騒音語に逃げ込むかもしれない。
マックス・ピカートというスイスの哲学者はこう言った。
「何の目的もないおしゃべりというものは、他のおしゃべりの中に滅びてしまう。」
さて、どうすれば生きやすくなるのだろう?
——そのとき、ふと浮かんだ。
「普遍に焦点をあててみる」ということ。
「普遍」とは何か。
普遍とは、時代や場所、人や状況を問わず、常にどこでも当てはまること。
「広く、あまねく」行き渡ること。
それは、偏らず、すべてを包むような視点でもある。
理知はもちろん大切だ。
でも、起きた出来事を理知でほどく前に、
それが“誰かが懸命に生きた証”として起こったことだと見つめることができたなら。
その視点を持てたなら、少しだけ生きやすくなるのかもしれない。
「幸せは普遍か?」——そんな問いを考えたことがある。
ある日、知人がこう言った。
「俺は今、すごーく幸せなんだ…」
「毎日、うまいものが食べられて…」
「毎日、美味しい酒が飲めて…」
黙って彼の話を聞きながら、私は思った。
——彼はきっと、幸せなのだろう。
でも、その幸せは“普遍的な幸せ”とは、少し違う気もした。
享楽的な幸せ。それを幸せと呼んでいいのか。
もし私が享楽主義でなければ、同じようにそれを幸せだと感じられるだろうか。
そして、問いは深まる。
幸せとは、誰にとっても同じ形をとるものなのだろうか?
たとえば、美味しいものを食べている瞬間に感じる幸せ。
それは、普遍に触れているようでいて、実は“その瞬間だけ”のこと。
お酒も同じ。
程よく酔いながら、心がほどけていく感覚。
それもまた、刹那的な幸せだ。
そう考えると、享楽主義に基づく幸せは、やはり普遍ではないのかもしれない。
幸せの普遍とは、何に宿るのか?
それが、たとえば「ありがとう」という言葉の中にあるのではないかと思うのだ。
「ありがとう」は、誰かを大切に思う気持ちの表れであり、
与えられたもの、与えられた命に感謝する行為でもある。
この言葉の中で生きられたなら、
きっと私たちは、幸せの中に生きることができるのではないだろうか。
もし、何かが起きたとき。
理知でそれらを整理するよりも前に、
「ありがとう」と感じる視点で、
懸命に生きた出来事を見直すことができたなら。
そのとき、私たちは「普遍」と「理知」のあいだに橋をかけて、
ほんとうの幸せに触れられるのかもしれない。